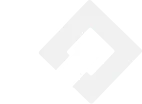御上神社・境内図Mikami Shrine
御上神社について
About Mikami Shrine

滋賀県野洲市三上に鎮座する御上神社(みかみじんじゃ)は、琵琶湖南岸の「近江富士」とも呼ばれる三上山(標高432メートル)の山麓に位置し、三上山を神体山として祀っております。三上山は、藤原秀郷(俵藤太)ムカデ退治の伝説(三上山伝説)でも知られています。
毎年10月に執り行われる秋季古例祭「ずいき祭」は、秋の収穫感謝と子孫繁栄を祈念する祭りで、鎌倉時代以前に始まったとされております。ずいきで作製したずいき御輿が奉納されるほか、芝原式では子供相撲が奉納されます。この祭は、中世の宮座の祭祀組織や神事を伝えており、平成17年に国指定重要無形民俗文化財に指定されております。県内外から多くの方にご参拝をいただいております。
ご由緒
History
神社名
御上神社
(みかみじんじゃ)
御祭神
天之御影命
(あめのみかげのみこと)
当社の起源は、第7代孝霊天皇6年6月18日に御祭神天之御影命が三上山に御降臨遊ばされ、それから約1,000年の間、御上祝(神主)等は三上山を清浄な神霊の鎮まる厳の磐境と斎定めて祀っており、『古事記』開化天皇の段に「近つ淡海の御上祝がもちいつく天之御影神」と記されている。
奈良朝初期元正天皇の養老2年3月15日(718年)に藤原不比等が勅命を拝し、榧木原と称された現在の鎮座地に造営して、御遷祀した。
以来、朝野の尊崇極めて篤く、陽成天皇の御代(877年~884年)には正一位の神階を授けられ、併せて社殿の修営も行われた。
次いで醍醐天皇(897年~930年)の延喜の制では、名神大社に列せられ、月次・新嘗の官幣社として記されている。
更に、円融天皇(969年~984年の)御代には当社を勅願所と定められた。
武家執政の世になっても、源頼朝を始め各武将も崇敬深く変わることなく、徳川幕府に至るまで、代々神領を寄進し、社殿の修営を行い尊崇が深かった。明治維新の神道復興の時運に際し、御社頭の整備が行われ、明治32年に本殿・拝殿・楼門が特別保護建造物に指定された機会に国庫補助を受けて解体修理の大事業が行われている。
大正13年に県社から官幣中社に列格される。
摂社・末社の御祭神
- ・摂社
- 若宮神社
-
伊弉諾尊
菅原道真公・天石戸別命・天御桙命・
野槌之神 - 三宮神社
- 瓊々杵尊
- ・末社
- 大神宮社
- 撞賢木厳之御魂天疎向津比賣命
(天照大御神の荒魂)・天照大神(和魂) - 鍵取神社
- 天津彦根命・猿田彦命
- 愛宕神社
- 火産靈神
- 竈殿神社
- 火産靈神・奥津比古神・奥津比賣神
- ・三上山
- 奥宮
- 天之御影命
- 八大龍王社
- 八大龍王神
文化財などについて
- 【国宝】 本殿(建造物)
- 【国指定重要文化財】拝殿(建造物)/摂社若宮神社本殿(建造物)
/楼門(建造物)/木造狛犬(彫刻) - 【国指定重要無形民俗文化財】 三上のずいき祭
- 【滋賀県指定有形文化財】摂社三宮神社本殿(建造物)/絹本著色両界曼茶羅図2幅(絵画)/木造相撲人形1組(力士2,行同1)(工芸品)/御上神社文書265点(書跡)
- 【野洲市指定有形文化財】 黒漆金銅装神輿3基
境内図
Precinct map

 境内図の建造物をクリックすると概要にジャンプします
境内図の建造物をクリックすると概要にジャンプします
建造物の概要
Overview of the shrine
-

国宝
御上神社 本殿桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、
向拝一間、檜皮葺建立年代は明らかではないが、様式手法からみて鎌倉時代後期の建立と推定される。入母屋造、漆喰壁及び連子窓など仏堂的要素が融合した神社建築で、簡素であるが優れた形をしている。
中心部一間四方を内陣として正面に板扉を構え、その周囲に一間通り化粧屋根裏の庇を廻らした構成だが、側柱の間隔はすべて同じで、内陣の柱間はその一間よりやや広くなっている。身舎(内陣)、側廻りとも隅柱上に舟肘木をのせ、向拝の蟇股は内部彫刻を失っているが、柱上連三斗の組物と共に力強く、手挟は珍しい形をしている。反花を刻んだ縁束石が並んだところは壮観で、その正面右端のものに建武4年(1337年)の刻銘(地中部分)があり、縁廻り及び向拝はこの時期に修理が行われたとみられている。
昭和27年11月22日には、滋賀県の神社建築としては最初の国宝に指定されている。 -

国指定重要文化財
御上神社 拝殿桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、
檜皮葺この拝殿は旧本殿の部材を再利用して建立されたものと云われている。本殿の柱間寸法と殆ど変らない規模で、隅柱上のみに舟肘木をもち、内部中央を棹縁天井に、その周囲を化粧屋根裏とし、軒は二軒繁垂木であり、入母屋の破風を小さく構えるなど本殿の様式とよく似ており、柱には旧柱間装置の仕口が残っている。様式等により鎌倉時代後期の建立と考えられる。面及び背面のそれぞれ中央間は内法長押を一面に張り、機能的に修理が行われたことがわかる。 -

国指定重要文化財
御上神社 楼門三間一戸楼門、入母屋造、檜皮葺
楼門は2階建ての門だが、腰組で廻縁を支え屋根は一重であって、屋根が上下二重になっている二重門とは区別される。平安時代は神仏習合の思想が特に発展し、神社にも楼門が建てられるようになったと考えられるが、現在では鎌倉時代以降のものしか現存していない。
建立年代は諸説あるが、この門の上層間斗束裏面に「かうあん5年きのとみのとし」の墨書があり、乙巳は康安5年(1365年)に当たり、各部の形式も当時のものとみられることから、室町時代の建立と考えられる。楼門としては最も普遍的な、三間一戸楼門で、全体は和様であるが、上層の頭貫に木鼻をつけたのは禅宗様細部の混用されている。組物は上下層共三手先だが、楼門の上層三手先組物に尾垂木が無いのは珍しい形式である。
摂社
-

国指定重要文化財
御上神社 摂社 若宮神社本殿一間社流造、檜皮葺
流造本殿は神の座を設ける母屋に縁を廻らし、正面に木階をつけ屋根を全体に延ばして木階を覆うと共に拝礼の場を作ったもので、屋根は流麗な曲線に発達した。全国的に分布し、一間社流造は三間社流造に次いで遺構が多い形式。
この本殿の建立年代は明らかではないが、鎌倉時代後期のものとみられ、規模は中型で浜床を低く作る形式は古式に属している。母屋の円柱上には舟肘木をのせ、向拝は大面取の方柱で連三斗の組物をのせ、母屋柱との間に繋虹梁をかけている。向拝には内部彫刻の簡単な古式的な本蟇股を飾り、全体的に明快簡素な建築となっている。 -

県指定有形文化財
御上神社 摂社 三宮神社本殿一間社流造、檜皮葺
建立年代は室町時代。御上神社の摂社で「十禅師社」とも称した。構造形式は若宮神社と似ており、蟇股には牡丹の透彫が入っている。
末社
-

大神宮社
御祭神 撞賢木厳之御魂天疎向津比賣命(天照大御神の荒魂)・天照大神(和魂)
例祭日 1月16日 -

鍵取神社
御祭神 天津彦根命・猿田彦命
例祭日 5月16日 -

愛宕神社
御祭神 火産靈神
例祭日 7月23日 -

竈殿神社
御祭神 火産靈神・奥津比古神・
奥津比賣神
例祭日 3月27日
-

神輿庫
野洲市指定有形文化財 黒漆金銅装神輿
(大宮神輿・若宮神輿・十禅師神輿)この3基の神輿は、当社例祭の神幸式(神輿渡御)に用いられていたもので、定形造の屋根に鳳凰を戴く黒漆金銅装の鳳輦神輿。大宮神輿がやや大きく、若宮神輿・十禅師神輿は形状・法量がほぼ一致する。若宮神輿と十禅師神輿の台框裏面には寶徳2年(1450年)卯月日の墨書銘があり、3基とも室町時代前期の製作とみられる。江戸時代初期(1620年代)に外観を整える修復が行われているが、室町時代前期の神輿がそのまま遺され、県下でもきわめて希少なものとして野洲市の文化財に指定された。 -

社務所・授与所・祈祷受付
【授与所・祈祷受付】
- ●授与所受付時間
- 午前8時30分~午後5時
(早く閉まる場合がございます) - ●祈祷時間
- 午前9時40分~午後3時40分(20分毎)
最終受付は午後3時30分
(希望時間の15分前には受付へお越し下さい。)
祭礼等により、祈祷時間や祈祷場所に変更がある場合がございますので、祈祷カレンダーをご確認下さい。 - 御祈祷カレンダーはこちら

-

三上山 奥宮
御祭神 天之御影命
例祭日(山上祭) 旧暦6月18日 -

三上山 八大龍王社
御祭神 天之御影命
例祭日(山上祭) 旧暦6月18日
兼務社

野蔵神社(のくらじんじゃ)
【鎮座地】〒520-2322
滋賀県野洲市南桜1
【御祭神】木之花佐久夜比賣命
(配祀神)大山祇神 宇迦御霊神 豊受大神 大佐須良命 苔虫命 野槌神 菅原道真公 足志那比売命 大山咋命 足志那勝彦命 迦具土命 天照皇大神(境内社御祭神)誉田別命(応神天皇) 息長足姫命(神功皇后)
【御神紋】三ッ巴 十六葉裏菊花門
【御由緒】社伝によれば、桓武天皇延暦3年社殿建立祭神奉斎と伝え、文徳天王仁寿元年に、正六位上、元禄17年に正一位の神階を受ける。歴代領主、崇敬者の信仰は篤く、南北朝時代には、宋版大般若経六百巻、絹本釈迦十六善神画像などの施人、田地の寄進を受けている。江戸初頭、領主稲垣摂津守から神領五反、八幡山三町歩余が寄進された。ついで、廣幡内大臣家がこの地を治め、明治に至るまで、折々奉幣使を派遣され、守護神も勧請されている。
【本殿・境内建物】本殿一間社流造
間口一間 奥行一間拝殿入母屋造 間口三間 奥行三間
【境内社】八幡神社
宇佐神社
【例祭日】5月 5日
三上神社(みかみじんじゃ)
【鎮座地】〒520-2332
滋賀県野洲市妙光寺1
【御祭神】天之御影命
【御神紋】釘抜紋
【御由緒】社伝には三上山麓に天之御影命が降臨になったと伝えている。古来から御上神社の外8社の1社が奉斎されていた。現社殿は寛文6年に造営された。同時期に築造された約一町歩の田用水源である妙光寺池の守護と産土神である。
【本殿・境内建物】本殿一間社流造
間口三尺 奥行三尺拝殿入母屋造 間口二間 奥行二間
【境内社】若宮神社
十禅師神社
【例祭日】 5月 5日